眠りたいのに、眠れない?不眠症とは

私たちの人体には意識的に動くものと無意識で働く機能があります。意識的に動かすものといえば、歩いたり、ものを掴んだり、話したり、ということですが、無意識的に働くものといえば心臓の鼓動、消化、吸収、排泄などをあげることができます。
今回のテーマである「睡眠」も副交感神経が働くことで無意識に行われていますが、強いストレスやプレッシャーを感じたり、自律神経の失調、うつ病など様々な要因で不眠症に陥ることがあります。
またそういった疾患が原因でなくてもふと、どうやって眠ってたかな?というのが気になってしまったり、考え事をしていて眠れなくなってしまうなどなど、眠れないという経験は誰にでもあるものだと思います。
今回はそんな不眠症のアレコレについて記事を書いてまいりたいと思います。
不眠症とはどういった症状?

ざっくりと言えば不眠症とは「夜に眠れない」状態のことですが、もっと細かく分類することもできます。つまり、眠りにつけないのか?早く起きてしまうのか?夜中に目が覚めてしまうのか?そして寝ても身体が回復しないのか?という事です。
それぞれを入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害という言い方もします。
この中で、一番の問題になるのは入眠障害だと思います、また改善が難しいのもこの障害ですね。原因は冒頭で挙げたもの以外でも様々に考えることができ、大別すると「病気によるもの」「生活習慣の乱れ」「心の問題」があると思います。
病気によるものとは冒頭のような神経、精神の病だけではなく、身体の不調も含まれています。例えば、皮膚のかゆみやふしぶしの痛み、頭痛、循環器の不調など違和感や、痛みを常に感じているとすぐに眠ることが難しくなります。
生活習慣の乱れは昼夜逆転・不規則な生活、偏った食事、飲酒、などを指します。特に昼夜逆転生活を繰り返している方は生活リズムを崩し、自律神経の乱れ、あるいはメラトニンというホルモンの分泌が減少してしまいます。
メラトニンというのは夜に多く分泌されるホルモンで睡眠ホルモンとも呼ばれます。このメラトニンは分泌量の増減によって睡眠と覚醒を切り替える働きを持っており、自然に眠りにつくのに欠かせないホルモンです。
ちなみにですが、このメラトニンは加齢と共に分泌量が減っていきます。その為、年を取っていく毎に長時間眠れなくなったり、早朝に目が覚めてしまうのです、加齢によって眠れなくなる原因にはこのような理由があるんですね。
最後に心の問題です。これは例えば試験のプレッシャーや次の日に大切な商談を控えて興奮してしまったり、あるいは単純に仕事・人間関係のストレスを感じて眠れなくなっている状態です。心の問題は多くの場合、自分以外の周囲の人間が関係していることが多いと思います。
周りの環境はなかなか自分一人では変えることができません。本来であればストレスの原因を根絶することが望ましいですが、それが出来ない環境にある場合は整体など他人の力でリラックスしてみたり、汗をかくような運動を日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
不眠症を改善するには?

これは原因にもよるので一概にはいい難いですが、まずはメラトニンが分泌される状態を作り出せるようにしてみましょう。具体的に言えば寝る前には部屋を暗くする、スマホ・パソコンを見ない、リラックスできる環境を作る、といった事が大切です。
つまり、最良の手立ては部屋を暗くして暗い中で「読書」をすることだと思います。そもそもスマホ・パソコンがなぜ不眠症を引き起こすかというと液晶が放つブルーライトという光が良くないのです。
この光が目に当たる事で交感神経(日中、活動するために働く神経)を活発にし、副交感神経・メラトニンの分泌を低下させてしまうのです。その結果、身体はまだ昼間であるというご認識をして不眠症に陥ってしまうというわけです。
さらにいえばこの光は放出体から近ければ近いほどその効果が強いので物体と目の距離が近いスマホは不眠症にとっては一番よくないということです。
それから入眠障害ではなく長時間寝ても次の日に疲れを持ち越している、眠気が襲ってくるといった熟眠障害をお持ちの方は、食事に気をつけましょう。特に寝る前に暴飲暴食をすると身体は睡眠し、回復することではなく、身体に入ってきた食品を消化・吸収することに力を使ってしまい、休まりません。
まとめ
本日は誰にでも経験がある「不眠症」について記事を書いてまいりました。不眠症も立派な病気なのでメリットは当然ないわけですが、不眠症に掛かると寝られずにイライラし、日中も眠気が襲ってイライラし、そのイライラによってまた眠れなくなってしまう。といった負の連鎖が起こってしまう可能性があります。
今回、提示したような改善策を行ってみても全く改善が見られない時は、ご自身だけで悩まずにお気軽に当院へご連絡ください。
病気の有無、精神的病、肉体的疲労の程度などをキチンとお伺いして、お客様に最適な改善策が提示できるかもしれません。




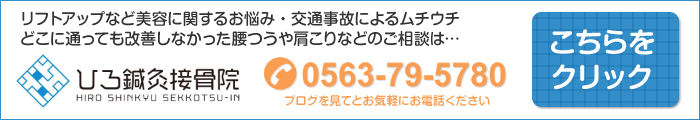
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません