肩こりは身体の緊張からも現れる!?生活習慣には注意しましょう!

誰にでも起こり、誰もが経験があり、私たちに非常に身近な不調と言われると「肩こり」を思い出す人が多いのではないでしょうか。
勉強のしすぎ、仕事のしすぎ、緊張のしすぎなど肩こりが発症する原因もさることながら、身体は一つながりで出来ていますので、頭、肩、胸、腕、などの肩と繋がっている組織の不調が原因で副次的に肩こりが発生することもありますし、精神的なストレスが原因で引き起こされる肩こりが存在することも確認されています。
また厚生労働省が提出しているデータでも自覚症状を感じる疾患を調べたところ、男女ともに肩こり、腰痛が最上位に上がっていますので、もはや日本人の国民病といっても差し支えないものだと思います。
しかし、寝ても覚めても肩こりが解消されず、重症化して痛みを伴うなどすると、仕事も家事も放棄してしまいたくなりますよね。今回の記事では一般的な肩こりのメカニズムやその解消法などをご紹介してまいりますので一緒に確認しましょう。
肩こりのメカニズム
冒頭で挙げたように肩こりの原因は日常生活のどこにでも潜んでいます。例えばプレッシャーを感じる営業マン、常に同じ姿勢をしているデスクワーカー、子供を抱える主婦の方々、猫背を始めとする悪姿勢が癖になっている方、運動不足などなど挙げればキリがありません。
ですからここでは一般的な肩こりが起こるメカニズムをご紹介しますのであくまで参考程度にご覧いただければと思います。まず初めに、骨格の話をすると肩回りというのは非常に多くの神経、血管、骨、スジ、腱などが組み合わさるように出来ています。
複雑な構造になっているので私たちは肩を回したり、モノを投げたり、取ったり、腕を上げることが出来るのです。また人間の頭部というのは意外にも重く、体重のおよそ一割の重量があると言われています。
そんな重たい頭部を支えるのは頭部に比べて明らかに細い首になるわけですから、私たちの首には相当な負荷が掛かっているといえると思います。さらにいえばここを支える筋肉は寝ても覚めても活動を続けているため、とても酷使されやすい構造になってしまっているのです。
また肩部分に限らず筋肉を使うには、原動力となる酸素と栄養が必要不可欠です。この酸素と栄養素は血管を通して、血液に乗って運ばれることにより、体全体に供給され、活力をもたらしています。
通常、筋肉はポンプの様に緊張と弛緩を繰り返し、血流を歩進しており、正常ならば、何の障害もなく血液を円滑に循環しています。しかし、一部の筋肉が疲労によって緊張、硬直を起こすと、その周辺に行き渡る血液がスムーズに流れ込まれなくなります。
すると硬くなり、血流が悪くなった箇所に必要な栄養素や、酸素が上手く行き渡らなくなるので、筋肉に酸素不足が起きます。それによって乳酸など他の老廃物質が溜まっていき、細胞から発痛物質を発生して神経に触れた結果、コリや痛みを生じることになります。これが、肩こりを発症するまでのメカニズムというわけです。
肩こりの改善には?

肩こりを直すためにはやはり自分自身の生活を見つめなおしてみることが近道だと思います。無意識で悪姿勢になっていたり、スマホの使いすぎでいつも下を向いていたり、いかり肩になりながらデスクに向かっていたり、果ては重たい荷物を常に決まった手で持つ、などといった小さなことからも肩こりは起こります。
昨今では肩こりを改善する為の市販薬も多く出回っており、使ったことがある方も多いとは思うのですが、姿勢や日常生活の癖から来る肩こりは原因から改善していかないと再発を繰り返してしまいます。辛い肩こりにお悩みの方は原因を解明するためにも専門家に相談することをおすすめします。
では、肩こりの予防策ですが、月並みな見解になってしまいますが、やはり日常に運動を取り入れることだと思います。運動する事で得られる効果は身体の筋肉の緊張を解し、血流を改善できるだけではなく、継続させることで筋肉の低下を防止し、柔軟な筋肉を作れるようになります。
また身体を動かすだけでなく筋肉は、血液を体内に循環させるポンプのような働きをしているので、運動の継続は、全身の血流の流れを良くすることになり、それによって肩こりになりにくい体づくりができます。
その他に、筋肉量と質を維持する事で女性にとっては冷え性の予防にもなりますし、ストレスの発散、アドレナリンが放出されることでポジティブな気分で生活できるようになるなど、メリットは非常に多いと思います。
まとめ

今回は日本人の国民病ともいえる肩こりに焦点を当て、そのメカニズムや予防方法などについて記事を書いてまいりました。文中でも触れている通り、肩こりの原因は人それぞれ異なっていますので、お悩みの方は、ご自分の生活を見つめなおし、原因を探しましょう。
もしも、原因と思われることを改善したり、ご自身で出来る努力をしてみても一向に改善しない場合は、違った疾患の前兆であったり、肩回りに原因がない場合も考えられます。耐え難い肩こりに悩んだ時はお気軽に当院までご相談ください。




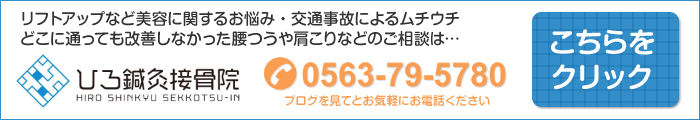
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません