月経のイライラに理由が?月経前症候群!
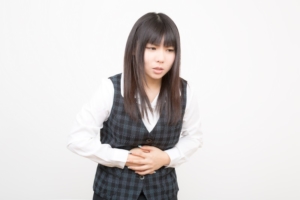
男女平等が叫ばれる昨今ですが、男女まったく同じ権利を有するのが平等と考える人もいれば欧米のように女性にある程度の配慮を加えるものが本当の平等であると考える方もいらっしゃると思います。
どちらの意見が正しいかは答えが出ませんが、男性に比べて女性は女性特有の悩みや肉体的な弱さは確かにあると思います。例えば年齢を重ねるほどに骨が脆くなったり、膝や脚に変形が見られたり、閉経によって女性ホルモンのバランスが乱れてしまうなどが挙げられます。
また男性には頭では理解できても経験がないので理解してあげられないのが「月経」に関係する毎月のわずらわしさやそれに関わる疾患などで、今回ご紹介する月経前症候群もその一つです。
この疾患は女性同士であっても理解することが出来ない時もありますし、多くの方にとって月経中は精神が不安定になったり、下腹部に痛みがあるのは自分にとって当たり前という認識を持っていたりして、疾患名を知らない方もいらっしゃると思います。
原因の多くはストレスやホルモンバランスの乱れからくると考えられており、今回の記事でご自身の痛みやイライラの原因が理解できるかもしれません。それでは始めてまいります。
月経前症候群(PMS)とは?
月経前症候群は冒頭で触れたように月経の前に起こるイライラや頭痛を伴う疾患で、月経前に現れ、月経が終わると収まるといった特徴があります。また同じような症状ですが、よりうつ病の傾向が見られたり、イライラから周囲に当たり散らしてしまう症状がでる月経前不快気分障害(PMDD)という疾患もあります。
これらの疾患の原因は現在の所まだ判明していませんが、月経前~月経中に症状が現れ、月経後にはぴたりと止むことからやはり女性ホルモンの異常からくるものではないかと推測されています。
女性の身体は月経が始まるとエストロゲンやプロゲステロンを分泌しますが、それらのホルモンは月経が終わりに近づくにつれて減少していきます。特にこのホルモンバランスの急激な変化が症状を引き起こされると考えられています。
月経前症候群(PMS)の症状は?

冒頭でも触れましたが、この疾患による症状は個人差がとてもあります。生理が始まって2.3日で気持ちが落ち着いてくる方もいらっしゃいますし、一週間、二週間という長い時間、症状が見られる方もいらっしゃいます。
また普段は温厚な方がこの時期になるとイライラが収まらず、他人に当たり散らしてしまうようになったり、情緒不安定、うつ感、注意力の低下、睡眠障害、乳房の痛み、むくみ、めまい、頭痛、肩こりや、肌荒れを始めとしたスキントラブルなども起こります。
あるいは月経前不快気分障害の場合はそれらに加えて、暗い気分が止まらなくなってやる気を失ってしまったり、悲しくもないのに涙が止まらない、攻撃的になって人やものに当たってしまう方もいらっしゃいます。
月経前症候群の症状が現れたら?
まずはご自身にとって、現在起きている症状が異常な状態であると理解することから始めましょう。どのような症状が起こって、普段の自分とどう違うのか。これは自分でなければわかりませんし、それがわからないと周りにいる人間もどのようにしたらよいのかわかりません。
また月に一回だからと放置したり、無理に我慢することは控え専門家に相談するなどの処置が望ましいと思います。家族に理解されないことはもとより、同性に相談しても賛同が得られないと自分がおかしいのではないか、といった孤独感が一層症状を悪化させてしまいます。
次にストレスを解消する方法を考えましょう。これもご自身の趣味嗜好によって様々ですが、そういったものをなにも持っていない、という方はこれを機会に探してみるのも良いかもしれません。
例えば運動を始めてみたり、紅茶について学んでみたり、読書してみたり、と趣味になりそうなものはそこら中にあるものです、ちなみにおすすめはやはり運動です。
運動の良いところは汗をかく爽快感が得られる事、代謝があがる、筋肉量が増えることで冷え性などの改善にもなります。またこれは運動に限ったことではありませんが、日常生活で目標を意識するとより効果的です。
日々の活動に目標を設定し、それをやり遂げることは幸せホルモンと呼ばれるドーパミンの分泌を促し、やる気の向上、ポジティブな精神状態を生み出してくれます。是非、試してみてください。
まとめ

今回は多くの場合、月経前に不快感やイライラ、情緒不安定をはじめとする身体の不調を引き起こす病、月経前症候群について記事を書いてまいりました。
文中でも触れましたが、月経特有の悩みというのは男性に限らず女性同士でもなかなか理解してもらえません。また理解されないと当たり散らしてしまったりして、せっかく築いた人間関係が壊れてしまうきっかけになってしまう可能性もあります。
まずは落ち着いて、ご自身の状況を理解し、そして周りに伝え、どういった対応をしてほしいのか、あるいはしてほしくないのかをキチンと伝えましょう。もしも、ご自分で努力をしても改善しない時はお気軽に当院までご相談ください。








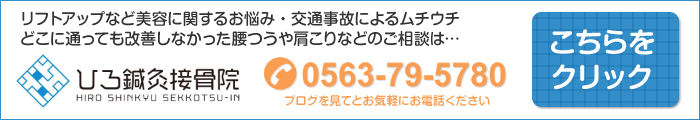
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません