原因は電解質?こむら返り!
 今年の夏は、コロナウイルスの影響から外出できないと嘆いていらっしゃるご家庭の方も多いと思います。しかし、そんな中でも三密を避けるため、なるべく広い娯楽場所として海を選んでお出かけされる方のニュースをみました。
今年の夏は、コロナウイルスの影響から外出できないと嘆いていらっしゃるご家庭の方も多いと思います。しかし、そんな中でも三密を避けるため、なるべく広い娯楽場所として海を選んでお出かけされる方のニュースをみました。
海で遊ぶことは大変楽しいことですが、お子様でも大人の方にも気を付けていただきたいのは、泳ぎに自信があるからといって沖まで泳いでいってしまい、足がつっておぼれるなどの事故です。
また原因を同じくして夏になると就寝中に足がつって目が覚めてしまうという方も多くおられると思います、いわゆるこむらがえりと呼ばれる現象ですね。これが起こる原因は体のイオンバランスが崩れたり、筋肉の緊張、あるいは冷え性、または加齢による筋肉の衰えなどです。イオンバランスの乱れは身体から汗が流れることによっておこるので特に夏場によく見られます。それでは詳しく見てまいりましょう。
こむらがえりとは?
 では、まず初めに「こむらがえり」の原因から見ていきましょう。冒頭で示したように一つは体のイオンバランスが崩れていくことが原因となります。
では、まず初めに「こむらがえり」の原因から見ていきましょう。冒頭で示したように一つは体のイオンバランスが崩れていくことが原因となります。
人体の多くは水分でできていることは既にご存知だと思いますが、大人の場合60%、幼児の場合80%が水分でできていると言われています。ただし、その水分は川を流れるような水分ではなく、水と電解質、つまりイオンが溶け合った体液からできています。
イオンとは水に溶けることで電気を通す物質になったり、細胞の浸透圧の調整、筋肉や神経細胞の働きなどつかさどる役割を持っています。そのため、この電解質が少なくなると生命に多大な影響を及ぼす熱中症やこむらがえりが起こります。主な電解質として挙げられるのはナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどです。
またこれは余談ですが、電解質がなくなることで熱中症を惹き起こす原因の一つとして自発的脱水症状があげられます。これは汗をかいているのに水分だけを吸収することによって、体が水分を放出せず汗をかかなくなり、体に熱がこもってしまう現象です。
先程申し上げたように電解質、つまりイオンは体にとってとても重要な役割を果たしていますのでこの濃度が水分によって失われると、それ以上を体外に出そうとせず、それによって水分のみを吸収しても汗が出なくなってしまうことを自発的脱水症状と呼びます。
こむらがえりとは? その2
 次に筋肉の緊張ですが、筋肉の緊張と言うと特に夏場は体の冷えによって生み出されます。毎年、メディアでよく熱中症が騒がれるので夏場は空調の効いた室内にいるように心がける方も多いと思いますが、例えば人の多い社内などは空調調節が上手くいかないと思いますので、長時間いる場合は注意が必要です。
次に筋肉の緊張ですが、筋肉の緊張と言うと特に夏場は体の冷えによって生み出されます。毎年、メディアでよく熱中症が騒がれるので夏場は空調の効いた室内にいるように心がける方も多いと思いますが、例えば人の多い社内などは空調調節が上手くいかないと思いますので、長時間いる場合は注意が必要です。
ちなみに「こむらがえり」や足がつると言うと「ふくらはぎ」を思い浮かべる方も多いと思いますが、これはその通りで「腓(こむら)」と言うのは「ふくらはぎ」のことを意味しています。
この筋肉が痙攣を起こすので「こむらがえり」と呼ばれるわけですね。また、ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれ、大変重要な器官ですのでふくらはぎの筋肉は過剰に伸びたり、収縮ができないように伸びすぎを防ぐ筋紡錘(きんぼうすい)、そして縮みすぎ防ぐ腱紡錘(けんぼうすい)の二つの組織がありますが、特に腱紡錘の働きが低下すると筋肉の異常収縮が起こりこむらがえりを引き起こします。
まとめ
今回は夏場に汗をかいたり体液を失うことで起こる、熱中症やこむらがえりについて記事を書いてまいりました。
既に文中にも登場していますが、足がつる現象と熱中症の原因と言うのは非常に似通っていますので、どちらも防ぐためには昨今、メディアでもよく言われているようにスポーツドリンクなど電解質を含んだ水分を小まめに補給すること、それから体の冷えの対策を行ったり、適度な運動によって筋力のアップをお勧めします。
例えば、ウォーキングやスクワット、あるいはストレッチなど血行促進と筋肉量の維持ができるものが最適だと思われます。また、今年はさほどでもないかもしれませんが、例年では河原でバーベキューをする時にお酒を飲みすぎて脱水症状が起こり、そのまま熱中症の症状が出てしまう方もいらっしゃいます。
長い時間外にいるときは炎天下を避け、木の下などにいるようにしましょう。それでは最後にこむらがえりの予防についてまとめているサイトを引用しておきますので、こむらがえりがよく起こる方はぜひ、実践してみてください。
足をつらないための8つの予防策
前後にストレッチをしたうえで、適度な運動→筋力アップ(例えばウォーキングやスクワットなど。足の筋肉量維持や血行促進に役立つ
運動前にスポーツドリンクなどで、神経の伝導に必要な電解質(イオン)を補給する
日頃から睡眠やストレッチなどで疲労回復&筋肉の緊張を解くこと
体の冷え対策の徹底(入浴や服装、食生活などで冷えをできるだけ改善)
水分をこまめに補給する(とくにお酒を飲むときは、水も飲んで脱水症状を防ぐ)
ミネラル不足にならないよう、バランスよく食事を摂る
足指の神経が圧迫されがちなハイヒールをよく履く人は、入浴後などに足指ストレッチをおこなう
普段から運動している人もしていない人も、1日の終わり(夜)にふくらはぎのマッサージなどのフットケアをおこなう








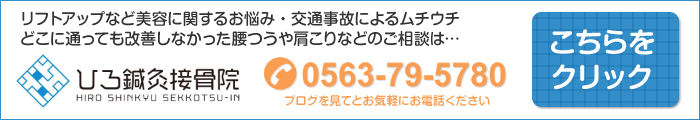
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません