不摂生は身体を痛める!肥満による腰痛!
 メタボリックシドロームという言葉が一般的になってからメディアはこぞって痩せることはいいことである、心身ともに健康な状態は痩せている方がいい。という言葉を聞く回数が増えたように思います。
メタボリックシドロームという言葉が一般的になってからメディアはこぞって痩せることはいいことである、心身ともに健康な状態は痩せている方がいい。という言葉を聞く回数が増えたように思います。
もちろん、その前からも飽食の時代を迎えてからは肥満は一つの社会問題になっており、昨今では適正体重を維持するためのアプリケーションや保険などが多くなりました。もちろん肥満体系になると心臓を始めとした内臓疾患や生活習慣病にもかかりやすくなってしまいますが、肥満はそれだけなく、腰痛や膝などにかかる負担を多くしてそういった箇所のケガをする機会が多くなり、日常生活にも影響を与えてしまいます。
今回は主に肥満と腰痛の関係を見ていきたいと思います。それでは記事を始めてまいります。
肥満はどこから始まる?その影響は?
 それではご存知の方も多いと思いますが、まずは肥満体系の基準について確認しましょう。肥満度を測るBMIという数値があり、その計算方法は、適正体重 = (身長m)2 ×22これで産出される値が18.5〜25未満ならば適正体重ですし、18以下は低体重となります。また数字によって肥満度合もわかり、25〜30未満、肥満(1度)、30〜35未満、肥満(2度)35〜40未満、肥満(3度)となっています。
それではご存知の方も多いと思いますが、まずは肥満体系の基準について確認しましょう。肥満度を測るBMIという数値があり、その計算方法は、適正体重 = (身長m)2 ×22これで産出される値が18.5〜25未満ならば適正体重ですし、18以下は低体重となります。また数字によって肥満度合もわかり、25〜30未満、肥満(1度)、30〜35未満、肥満(2度)35〜40未満、肥満(3度)となっています。
では次に肥満体系になるとどれほど身体に影響を及ぼすか、という事についてですが。私たちの身体は実は寝ていても起きていても、もちろん活動していても常に筋肉を使用しています。しかし骨格は変わりませんので、体重が増えれば自然と関節や腰など身体の基点となる所に負荷が蓄積されていきます。
また程度にもよりますので一概には言えませんが、肥満体になると立つ、座る、あるいは前かがみになった時に適正体重の2.5倍も身体に負荷をかけ、膝や腰への負担は3~7倍にも増えるといわれています。
BMI数値を基準にして身体にかかる負荷の割合を数値化しているサイトがありましたので、引用してみましょう。
BMI(肥満指数)25以上で肥満と判定される40代の男性の7%、女性の8%は「腰痛症」で受療したことがあり、高齢になると女性の受療が増える――日本医療データセンターがこのほど行った調査で、腰痛症と肥満は密接な関係があることがあきらかになった。
調査では、病院の健康診断を受けた30代から50代の男女5万5,221人のデータをもとに、BMI25以上の人と25未満の人が腰痛症で受療した割合を比較した。
その結果、BMI25未満の男性の受療率は30代が4.6%、40代が5.4%、50代が6.2%で、BMI25以上では30代が5.7%、40代が7.0%、50代が7.4%だった。どの年齢層でもBMIが高いほど受療率が高くなる傾向にあり、その差は1.1~1.6%だった。
女性では、BMI25未満の30代が5.5%、40代が6.4%、50代が8.4%で、BMI25以上では30代が8.0%、40代が8.0%、50代が10.4%だった。
BMIの高い人や高齢の人ほど受療率が高くなる傾向は男女で変わらなかったが、年齢層による差は女性では1.6~2.5%に及び、男性より高い割合を示した。
引用:日本生活習慣病予防協会
以上のようにやはりBMI数値によって腰痛を含む関節痛は助長されていき、適正体重であればちょっとしたストレッチ、運動によって解決する問題が、先に肥満対策から行わなければならなくなり、改善に時間がかかってしまうようになります。
痩せるのは難しいというけれど、、
 ここまで読んでみると、では痩せてみようと一瞬だけは考えるけれど実際に行動を起こすのは大変、、と思っていらっしゃる方もいると思いますが、実は身体や脳が喜ぶ方法をキチンと取れば運動を続けていくことは、絶望的に大変というわけでもありません。
ここまで読んでみると、では痩せてみようと一瞬だけは考えるけれど実際に行動を起こすのは大変、、と思っていらっしゃる方もいると思いますが、実は身体や脳が喜ぶ方法をキチンと取れば運動を続けていくことは、絶望的に大変というわけでもありません。
例えば昨今、テレビやメディアで有名人がジムに通ってダイエットや肉体改造に成功した、というバラエティ番組が多くありますね。ダイエットや筋トレに励んだことのない方は往々にして彼・彼女の努力はすごい。という評価をします。
もちろん、素晴らしい努力の成果なのは間違いありませんが、成功した方々がすべからく意志が強いので成功したのではありません。実は筋トレは楽しいものなのです。
どういうこと?となってしまうと思いますが、それは筋トレは目に見えて努力の成果が出やすく身体の変化を感じやすいこともありますが、筋トレをしようと思えばほぼ全ての方々は「腕立て伏せを〇〇回やろう」「腹筋を〇〇回やろう」と回数やセット数、時間などを決めてトレーニングをします。
その理由は目標がないと何度やっていいかわからないからです。当然ですね。しかしこの目標を決め、それを達成するという行為は人間にとってとても気持ちがいい現象を引き起こします。それがドーパミンシステムです。
ドーパミンシステムというのは目標を決めてそれを達成することで、腸内で幸せホルモン(ドーパミン)が生成され、多幸感(気持ちがいい・すっきりする・幸せな気分)を得る事できるシステムです。
もちろん、これは運動でなくて勉強などでも発生しますが、筋トレは目標達成の回数が早く、一週間も続けていると明らかに一日前よりも二日前よりもこなせる回数が増加することでより、たくさんの多幸感を得ることができ、回数が増加することで目標が上がり、それをさらに達成することで多幸感が、、、、というように良いスパイラルが出来るからです。
運動はいきなり行うとケガをしてしまうこともありますから、無理しないように少しずつ始めて、多幸感やすっきりとした感覚をつかんで、運動は楽しいものであると思えるといいですね。








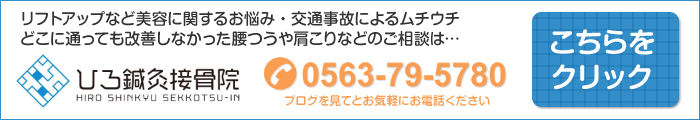
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません