中腰は問題を引き起こす?仙腸関節障害!!
 日本ではもちろん、多くの方がそれぞれの職業について働いているわけですが、概ね、ある職業に就くと特有の姿勢や行動を常に行うようになります。例えばデスクワーカーの場合は座っている機会が多いですし、建設業界であれば重たい荷物を運んだり、同じ作業を繰り返し行うようになります。
日本ではもちろん、多くの方がそれぞれの職業について働いているわけですが、概ね、ある職業に就くと特有の姿勢や行動を常に行うようになります。例えばデスクワーカーの場合は座っている機会が多いですし、建設業界であれば重たい荷物を運んだり、同じ作業を繰り返し行うようになります。
ですから職業によって起こりやすい不調、つまり職業病というものが存在すると思います。これはもちろん同じことを繰り返すスポーツなどでも起こるわけですが、今回は先ほどのように座りっぱなしであったり、反対に立ちっぱなしであったり、という方によく起こる仙腸関節障害というものをご紹介していきたいと思います。
あまり耳慣れない言葉だと思いますが、仙腸関節というのは骨盤にある関節で、これが緩んだり、ズレたり、反対に閉まったりして、腰回りに様々な症状を引き起こす疾患です。もちろん、常に同じ行動を繰り返すだけでなく、大きく尻もちをついたり、事故にあったり、他人と接触したりしてもおこりますので、腰痛とは異なる痛みや違和感を感じた時はこの疾患も疑ってみてください。
仙腸関節障害について
 ではまず仙腸関節がどこにあるのか?という話ですが、冒頭のように骨盤の中に存在しています。人体模型をご覧になったことがある方はお分かりかもしれませんが、人間の身体は頭骨から始まって、背骨、骨盤、そして下半身の骨というようにつながっています。
ではまず仙腸関節がどこにあるのか?という話ですが、冒頭のように骨盤の中に存在しています。人体模型をご覧になったことがある方はお分かりかもしれませんが、人間の身体は頭骨から始まって、背骨、骨盤、そして下半身の骨というようにつながっています。
そして骨盤の中にある背骨の執着地点の事を仙骨(せんこつ)と呼び、いわゆる骨盤を形成する大きな骨を腸骨(ちょうこつ)と呼びます。そしてこの二つの骨の接点にあるのが仙腸関節です。しかし、よくよく考えると私たちは腰が回せて足も動かせますが、骨盤を動かすことはありません。
もちろん、大切な内臓を支えたり、身体の中心になっている骨ですから動いてもらっては困るわけなので、この仙骨と腸骨は周りの靭帯によって強く繋がれています。つまり本来は動かないはずの二つの骨がズレてしまっているのです。
それによって腰痛、麻痺、腰の疲れ・違和感に始まり、重症化すると腰痛よりも若干、下部に痛みを感じたり、下肢のしびれや痛みを感じるようになります。
仙腸関節障害になりやすい方と対応策
 冒頭にもありますが、例えばデスクワーカーように座りっぱなし、反対に美容師、店頭販売員などの立ち仕事をされている、あるいは特に多いのが保育士や介護士、建設作業員のように中腰の姿勢でいることが多く、さらに中腰のまま子供やお年寄りを抱き上げるなどの作業を行う方々です。
冒頭にもありますが、例えばデスクワーカーように座りっぱなし、反対に美容師、店頭販売員などの立ち仕事をされている、あるいは特に多いのが保育士や介護士、建設作業員のように中腰の姿勢でいることが多く、さらに中腰のまま子供やお年寄りを抱き上げるなどの作業を行う方々です。
あるいは猫背を始めとする悪い姿勢で常にいる方も同様です。猫背以外でも巻き肩やストレートネックなど前傾姿勢に常になっている方は腰に負担を掛けるので腰痛になってしまう方が多く、さらに言えば肩こりにもなりやすいですし、肺が圧迫されることによって酸素不足に陥り、仙腸関節障害だけでなく集中力の欠如や、やる気の低下なども引き起こす可能性があるので、是非、改善しましょう。
仙腸関節障害の予防にはやはり腰を使いすぎないことが重要で、どうしても中腰になる場合は前傾に倒れていくのではなく、スクワットをするように垂直に膝を曲げてみたり、それがかなわない時はコルセットなどを使用して極力、腰の負担を減らすことが大切です。
また疲労がたまった腰にはストレッチも有効です。以下には仙腸関節障害にかかった方が行ったストレッチをご紹介します。
Aさんが治療としてチョイスしたのは、仙腸関節の負担を軽減するエクササイズです。
まず行ったのは、骨盤を支えるコルセットのような働きをする「腹横筋」という筋肉をうまく使えるようにするための「ドローイン」。仰向けに横になり、1メートル先の壁に向かって息を吹きかけるようなイメージで、ゆっくり息を吐いていきます。すると腹横筋が収縮して鍛えられます。
もうひとつは、太ももの裏にある筋肉「ハムストリング」のストレッチです。腸骨を後ろから支えるハムストリングが硬くなっていると、体を前傾したときに腸骨が十分前に倒れないために仙骨だけがさらに前に出て、仙腸関節に痛みが出てしまうのです。このハムストリングを伸ばすストレッチは、まず膝を伸ばし、骨盤を立て、背筋を伸ばして床にすわります。そして腕を前に伸ばし、骨盤から倒しながら前傾していきます。
引用:NHK健康チャンネル
まとめ
今回は特に中腰によくなる方に起きやすい仙腸関節障害について記事を書いてまいりました。文中にもあるように腰はよく使われることによって知らず知らずのうちに疲労が蓄積してしまうものです。
なるべく負担をかけないことはもちろん、運動後にクールダウンを行うように一定時間、あるいは帰宅してからストレッチをしてあげると疲労物質が流され、翌日に持ち越す疲労が軽減されますので、是非、実践してみてください。








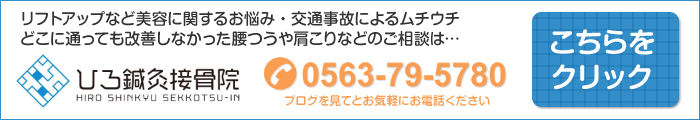
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません