疲労骨折に注意!ジョーンズ骨折!
 骨折という単語を聞くと、交通事故や他人との衝突や転倒などを連想する方が多くいらっしゃると思います。しかし意外とご存知ない方が多いですが、例えば骨同士が剥がれてしまったり、ヒビが入るといったことも立派な骨折の一つです。
骨折という単語を聞くと、交通事故や他人との衝突や転倒などを連想する方が多くいらっしゃると思います。しかし意外とご存知ない方が多いですが、例えば骨同士が剥がれてしまったり、ヒビが入るといったことも立派な骨折の一つです。
あるいは座りっぱなしの仕事をしている方は背骨にヒビが入ったり、骨がつぶれてしまう圧迫骨折などにも注意が必要ですし、サッカー、バスケットボール、ラグビー、卓球、バトミントンなどストップ&ゴーが多かったり、左右に身体を振るような競技をしている方々は今回ご紹介する疲労骨折の一つ、ジョーンズ骨折にも気を付けましょう。
スポーツをしているとケガが付き物ですが、こういった疲労骨折や膝の疾患などは初期段階ではあまり痛みが出ず、放置されてしまう事がよくありますから、当記事を読んでご自身に症状が当てはまる時は安静にして専門家に相談するようにしましょう。それでは記事を始めてまいります。
ジョーンズ骨折はどうして起こる?
 ジョーンズ骨折というのは主に第5中足骨(ちゅうそくこつ)の骨折。つまり足の小指の付け根に発症する疲労骨折です。例えば冒頭のように左右の動きが多く、足の外に圧力がかかったり、ストップ&ゴーを繰り返すことで発症します。
ジョーンズ骨折というのは主に第5中足骨(ちゅうそくこつ)の骨折。つまり足の小指の付け根に発症する疲労骨折です。例えば冒頭のように左右の動きが多く、足の外に圧力がかかったり、ストップ&ゴーを繰り返すことで発症します。
ジョーンズ骨折だけではありませんが、こちらも冒頭のように疲労骨折は人によって症状がバラバラでヒビが入っていても全く痛みが伴わない方もいらっしゃいますし、完全に折れていても違和感しかなく痛くないといった方もいらっしゃいます。
また先の原因だけでなく、自分に合わない靴や硬い靴を履いている、あまり整備されていないグラウンドでハードなトレーニングを行う事でも起こりますし、個々人の足の形や身体の作りによっても起こることがあります。
もちろん、プロの選手にも起こりますから定期的に検査を行っている団体もあるほどですが、やはり自分の身体や力量についてよくわかっていなかったり、周りに合わせる、あるいは周りに負けたくない、といった気持ちが強い学生の方々に起こりやすいと言えます。
ジョーンズ骨折を予防するには?
 中高生の場合はご自身でグラウンドの整備や質を変えることはできないと思いますので、まずは靴選びやプレースタイルの変更から取り組まれるといいと思います。
中高生の場合はご自身でグラウンドの整備や質を変えることはできないと思いますので、まずは靴選びやプレースタイルの変更から取り組まれるといいと思います。
例えば柔らかすぎる靴は左右の動きを行うと靴底のグリップを側面の素材が吸収できず足に負担を掛けるようになってしまいますし、同様に硬すぎる靴も左右の付け根に圧力をかけすぎてしまうので、自身の足に合うシューズ選びをしましょう。
あるいは硬いグラウンドやアスファルトで常にランニングをしなくてはいけない場合、ランニングシューズに履き替えて活動を行ったり、靴自体が取り替えられない時は衝撃を緩和する中敷き(インソール)なども最近では安価で買えるのでそういった改善方法もよいかと思います。
他にも以下のように食事に気を付けてケガ・骨折をしにくい身体作りをしてみるのもおすすめです。
中学生・高校生は特に食生活の見直しが大切
中学・高校の競技者に発生する疲労骨折の理由の一つは、エネルギー不足です。
「朝練に間に合わないので、朝食を抜く」
「夜は疲れてしまって、たくさん食べられない」
「お昼は菓子パンで済ます」
と話す選手が多くみられます。
このような食生活では栄養が十分に摂れず、運動に必要なエネルギーも足りません。
エネルギー不足が続くと骨の代謝にも影響を及ぼします。
成長期の中高生時代に骨が弱くなることは、将来的な骨の健康にも好ましくありません。
やるべきは食事をしっかり摂ること。
米、肉、魚、卵、乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズなど)、緑黄色野菜、海藻類、果物などバランスの良い食事を心がけましょう。
一斉休校のあおりで牛乳の生産酪農家さん等への悪影響が生じている今、乳製品を積極的に消費することは、社会貢献の一つにもなるように思います。
しっかり食べて、疲労骨折に負けない強い身体をつくりましょう。
まとめ
今回は足の小指の付け根に発症する疲労骨折、ジョーンズ骨折について記事を書いてまいりました。文中にもあるようにもちろんプロになっても気を付けなくてはいけませんが、特に中高生におこりやすい骨折です。
ジョーンズ骨折に限らず身体がまだ出来上がっていない、あるいは伸長していく段階にある身体はかかとが痛むシーバー病、膝に痛みを感じるオスグッド症などその時期特有の発症しやすいケガがあります。
またその時期は、まだ大きなケガをしたことが無い子も多く、痛みやケガに対する恐怖が少ない傾向があり、保護者・監督者の方々はよく観察の上、足を引きずるようにしていたり、かかとを不自然にあげるような歩き方をしている場合はプレーを中止し、よくよくコミュニケーションを取ってみることをお勧めします。








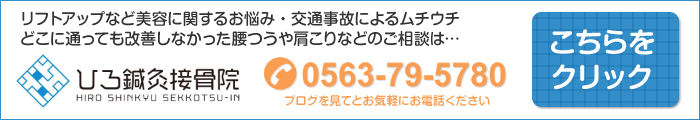
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません