成長期のケガは一生もの!?野球肩!
 昨今の日本では少しお金をかければどのようなスポーツでも楽しめる環境が整っています。もちろんそれは大人だけでなく子供にとっても同じで、珍しいスポーツを普及させようと努力している方も多くいらっしゃいます。
昨今の日本では少しお金をかければどのようなスポーツでも楽しめる環境が整っています。もちろんそれは大人だけでなく子供にとっても同じで、珍しいスポーツを普及させようと努力している方も多くいらっしゃいます。
しかし、日本で根強い人気のスポーツといえばサッカーか野球だとどなたもお答えになるのではないでしょうか。今回はそんな野球にまつわるケガ、特に成長期の子供たちが起こしやすい肩の不調について記事を書いていこうと思います。
四十肩を経験されたことがある方はご存知だと思いますが、日常的に肩というのは意外なほど使用されていて高い所の物を持つのはもちろん、洗濯していたり、身体を洗う時などにも使われるのでその時に痛みを感じると大変不便になります。
また先のように今回ご紹介する野球肩という不調は成長期に起こりやすいので友人と遊ぶ時や授業で手を上げる時なども不便を感じることでしょう。しかしこの不調は大抵の場合、肩より上に手を上げなければ痛みが走ることは少なく多くの場合、放置されてしまいガチです。成長してから後遺症で悩まないよう、しっかりと改善できるようにしましょう。それでは記事を始めてまいります。
野球肩ってどんな肩?
 野球肩という名前ですが、もちろん野球をしているからといって必ずなるわけでもありませんし、野球以外のスポーツでも起こりえます。それは例えば肩を回す水泳やハンドボールなどをしていてもなることがあります。
野球肩という名前ですが、もちろん野球をしているからといって必ずなるわけでもありませんし、野球以外のスポーツでも起こりえます。それは例えば肩を回す水泳やハンドボールなどをしていてもなることがあります。
そしてそれらのスポーツをやり過ぎることで、肩関節周辺に炎症を引き起こし、痛みを発生させるケガの総称をこのように呼びます。総称といういい方をしているのは厳密に肩のどの部位が痛いというよりは肩回りに炎症が起こっている状態だからです。
肩というのは前後左右に動かすことが出来る非常に可動域の大きな関節なのですが、その分、複雑でケガをしやすい構造をしていると言えます。野球肩の多くは骨と骨を繋ぐ腱に異常が見られたり、骨同士を摩擦させずにスムーズに動かす滑液包(かつえきほう)が原因で関節同士がぶつかり合い衝突し、炎症を起こして痛みを発生するものが多いです。
また特に成長期の野球選手によくみられるのが上腕骨近位骨端線離開(じょうわんこつきんいこったんせんりかい)と呼ばれるケガで別名:リトルリーグショルダーとも呼ばれています。
野球肩ってどんな肩?~その2~
 ではなぜ成長期の子供に起こりやすいのかというと、簡単に言えば身体が出来上がっていない状態だから、という言い方ができます。成長期の身体はいつの間にか徐々に大きくなっているように感じられますが、そうではなくて骨の伸長からまずは始まり、そして骨が伸びるに従って腱や筋肉が引っ張られ、大きくなっていくのです。
ではなぜ成長期の子供に起こりやすいのかというと、簡単に言えば身体が出来上がっていない状態だから、という言い方ができます。成長期の身体はいつの間にか徐々に大きくなっているように感じられますが、そうではなくて骨の伸長からまずは始まり、そして骨が伸びるに従って腱や筋肉が引っ張られ、大きくなっていくのです。
つまり成長期の身体というのは常に骨によって引っ張られている状態なのです、例えば大人になってもスポーツをやり過ぎると筋肉が硬くなり、骨と筋肉を繋いでいる骨膜(こつまく)という組織に炎症を起こし痛みを発生させることがありますが、成長期はすでに筋肉が引っ張られている状態でさらに運動によって負荷をかけることになるので、成長期特有のリトルリーグショルダーあるいは、同じような原因で起こる膝下の不調である、オスグッド症などにかかりやすくなる、というわけです。
まとめ
今回は成長期に起こしやすい野球肩について記事をかいてまいりました。文中にもあるように肩は非常に可動域の大きな関節なので構造も複雑に出来ており、ケガをしやすい部位です。
ケガの防止にはやはり筋肉を柔軟に保ってあげることが何よりですから、運動前の準備運動であったり、練習後のクールダウンは欠かさないようにしましょう。
また、そういったこと以外にもなにか予防策、あるいは痛みを軽減させる方法としてテーピングを行うという方法もありますから、そちらを最後にご紹介して終わろうと思います。
ピッチングで痛む場合
野球肩の発症は、ポジション別でいえば圧倒的にピッチャーの発症が多いです。
ですので、まずはピッチング時に肩が痛むという方向けのテーピング方法を紹介していきます。
ここでは、5cm幅のテープを2本貼っていきます。
剥がれにくくするために、テープの四隅を切っておくことがおすすめです。
ピッチング時に痛む場合は、肩の棘上筋と外旋筋をサポートすることが重要です。
1本目は、棘上筋がある、首と肩の真ん中あたりから肩の出っ張りまで貼っていきます。
2本目は、外旋筋に沿って、肩甲骨の端から肩の出っ張りまで貼ります。貼り終わりは、1本目のテープと重なるようにしましょう。
三角筋のテーピング
次は、三角筋のテーピング方法について紹介していきます。
三角筋は、上腕を内転・外旋させる働きがあるので、投球動作の際に非常に重要な役割を担っている筋肉です。
ここでは、3本のテープを貼っていきます。
1本目は、肘の上から、肩の出っ張っている部分を通って、首の付け根まで貼っていきます。
2本目は、1本目の貼り始めた箇所の少し前からスタートし、肩の出っ張りを通って、肩甲骨まで伸ばします。
3本目は、1本目の貼り始めた箇所の少し後ろからスタートし、肩の出っ張りを通って、胸まで伸ばします。
引用:TENTIAL






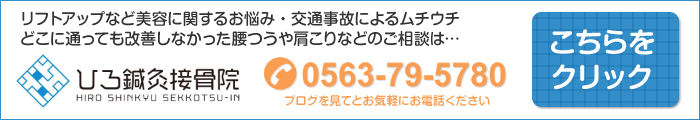
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません