最近あばら骨が痛い?それは肋間神経痛かもしれません!
 身に覚えのない痛みというのはどなたにとっても驚くものだと思います。例えば心臓がいきなりズキッと痛くなったり、頭痛、ギックリ腰などがそうです。しかし痛みには理由が判明しているかいないかにかかわらず原因が存在するものです。
身に覚えのない痛みというのはどなたにとっても驚くものだと思います。例えば心臓がいきなりズキッと痛くなったり、頭痛、ギックリ腰などがそうです。しかし痛みには理由が判明しているかいないかにかかわらず原因が存在するものです。
また昨今ではストレスでも身体に不調が起こることが判明していますし、姿勢が悪い事で腰の痛みであったり、膝の変形、足裏の魚の目や外反母趾などが起こることもあります。今回ご紹介する肋間神経痛はストレスや過去の骨折、身体の歪みなどが原因で発症し、先のようにいきなり痛くなることがあるあばらの痛みを総称する単語です。
後述していきますが、総称という言葉を使う理由は様々な原因から起きる可能性があるからで、原因の特定が難しいものであるからです。本文をお読みいただき、ご自身に当てはまる時は一度、専門家に相談してみることをおすすめします。それでは記事を始めてまいります。
肋間神経痛とは?
 冒頭にも総称という言葉が使われているように肋間神経痛は厳密にいえば正式な疾患名ではありません。肋骨(あばら骨)付近に張り巡らされている肋間神経に痛みが走ることを肋間神経痛と呼んでいるのです。
冒頭にも総称という言葉が使われているように肋間神経痛は厳密にいえば正式な疾患名ではありません。肋骨(あばら骨)付近に張り巡らされている肋間神経に痛みが走ることを肋間神経痛と呼んでいるのです。
その痛みは人によって個人差がありますが、ビリビリとした痛み、大声を出すとズキッと痛む、胸や肋骨に鈍痛がある、息がしづらく感じるなどといった症状が現れます。
また血管や肺・心臓といった内臓の疾患とは異なり、痛みが起きるのはいつも一定の場所で、左右どちらかの肋骨に痛みが走り、両側が痛むことはあまりないというのが特徴的です。
この痛みの原因はストレスなど心因性のもの、外傷的なもの、神経に異常を来しているものなどがあるのですが、ご自身に覚えがある場合は下記のチェックリストを確認してみてください。
肋間神経痛チェックリスト
下記の症状に当てはまる方は、肋間神経痛の可能性があります。
背中から脇腹、胸部やへそ周辺等(肋骨に沿って起こる)に、電気が走るような痛みや、ジクジク、ヒリヒリ、ピリピリするような痛みが続く(帯状疱疹による場合もある)。
上半身の左右どちらかのみに痛みが生じる。
痛みが生じていない方向に体を曲げて、肋間神経を伸ばすようにすると痛みが起こる。
上半身を前後に曲げる動き、左右に曲げる動き等に痛みが強くなり、息ができないくらいの痛みが起こる。
肋骨に沿って突如キューッとするような痛みが生じるが、数秒で痛みが消失する。
痛みが継続するケースがあり、触れただけで痛みを感じるような知覚過敏状態になる。
深呼吸、咳、くしゃみ、大きな声を出す等の肋骨が動く動作により痛みが生じる。
引用:EPARK
肋間神経痛の原因は?
 先にもあるように肋間神経痛の原因はストレスなど心因性のもの、外傷的なもの、神経に異常を来しているものなどが考えられます。心因性はストレスに端を発するものなのでわかりやすいと思いますが、神経の役割といえば私たちの身体を動かしたり、皮膚が熱や痛みを感じることが出来るのは神経のおかげです。
先にもあるように肋間神経痛の原因はストレスなど心因性のもの、外傷的なもの、神経に異常を来しているものなどが考えられます。心因性はストレスに端を発するものなのでわかりやすいと思いますが、神経の役割といえば私たちの身体を動かしたり、皮膚が熱や痛みを感じることが出来るのは神経のおかげです。
例えば中枢神経や末梢神経、有名な名前なのでご存知の方も多いと思いますが、背骨を通って全身に脳からの指令を伝える神経です。また反対に末梢神経が触れたものの感覚や、目で見えたもの、聞こえた音などを中枢神経に伝えることで感覚、聴覚、触覚などが成立します。
あるいは自律神経、こちらも昨今では有名になっていますが、心臓の鼓動、体温の調節、呼吸、食べ物の消化・吸収、排便といった私たちが普段意識せずに行っている生命活動を司る神経です。これらの神経に異常を来すことでちょっとした物事で過敏に反応するようになったり、痛みを感じるようになるのが肋間神経痛です。
あるいは冒頭のように外傷的な要因、例えば過去に交通事故や衝突事故で骨折して、骨が変形したままくっついてしまったり、日常的にデスクワーク、立ち仕事、重いものを持ちあげるといった仕事をこなしている方はその職業に合わせて姿勢が変化してしまうことがあり、そういった悪い姿勢をずっととっていると骨盤や背骨、あるいは肋骨に歪みが生じ、これによって肋間神経痛が発症してしまう可能性もあります。
まとめ
今回は過去の事故であったり、悪い姿勢、神経に異常が起きることで肋骨付近に痛みが起きる肋間神経痛について記事を書いてまいりました。文中でも触れているように肋間神経痛の症状や原因は多岐にわたり、身体の構造を知らない方にはなかなかその原因を探し出すことは難しい疾患です。
出来れば専門家に相談することが望ましいですが、ご自身で解決したい場合は、他の心因性の疾患にもいえることですが、運動をすることで症状が改善する場合があります。運動することは幸せホルモンといわれるドーパミンが分泌されたり、単純に汗をかくことでストレスの発散にもつながりますし、肉体的に疲れることで自律神経の調整が出来ます。
あるいは肋間神経痛だけに限らず、運動することで防げる疾患は非常に多くありますので、特に年齢を重ねた方は積極的に身体を動かすようにしましょう。








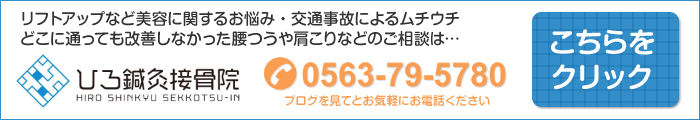
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません