不調の原因はどこにある?メンタルヘルス不調!
 働き方の改革が叫ばれるようになって、ずいぶんと経つように思います。以前は仕事は見て学ぶものだ、気合で乗り切るなど根性論や精神論が支配していた日本社会も様変わりを見せ、今ではキチンと理解できるように教える、社員が働きやすい環境を整える、職場環境の改善を常に行うなど待遇・処遇の改善は会社にとって非常に大切なマネジメントの一環となりました。
働き方の改革が叫ばれるようになって、ずいぶんと経つように思います。以前は仕事は見て学ぶものだ、気合で乗り切るなど根性論や精神論が支配していた日本社会も様変わりを見せ、今ではキチンと理解できるように教える、社員が働きやすい環境を整える、職場環境の改善を常に行うなど待遇・処遇の改善は会社にとって非常に大切なマネジメントの一環となりました。
しかしながら環境が変化したからといって、仕事や人間関係に対するストレスが皆無になったかといわれれば、そうでもないと誰もが話すものだと思います。もちろん、みんなで和気あいあいとした職場が一番いいとは言え、営業であれば数字を追わなくてはいけませんし、経理は数字を間違えてはいけない、人事は書類の管理をキチンとしないといけないなど、失敗することで多くの方に迷惑をかけてしまう事象は繰り返さないように注意が必要ですし、注意しないことは当事者が教える立場に立った時に困ってしまうことになります。
そのように他人と作業をしたり、会社の一部として働く時に出てきてしまうのがストレスで、これが全くない環境というのは少ないと言えます。中にはこのストレスを貯め過ぎてしまうことで起こる不調もあり、今回はその中でもメンタルヘルス不調について記事を書いていこうと思います。それでは始めてまいります。
メンタルヘルス不調とは?
 ストレス社会の現代においては、日本だけでも「メンタルヘルス不調」で通院している人がおよそ420万人ほどいると言われています。「メンタルヘルス(mental health)」とはその言葉通り「心の健康」、世界保健機関によると「自身の可能性を認識し、日常のストレスに対処でき、生産的かつ有益な仕事ができ、さらに自分が所属するコミュニティに貢献できる健康な状態」と定義していますから、「メンタルヘルス不調」とはこの状態を維持できないこと、つまり毎日のストレスとうまく付き合い、能力を発揮して社会に貢献できなくなっている精神状態のことを言うわけです。
ストレス社会の現代においては、日本だけでも「メンタルヘルス不調」で通院している人がおよそ420万人ほどいると言われています。「メンタルヘルス(mental health)」とはその言葉通り「心の健康」、世界保健機関によると「自身の可能性を認識し、日常のストレスに対処でき、生産的かつ有益な仕事ができ、さらに自分が所属するコミュニティに貢献できる健康な状態」と定義していますから、「メンタルヘルス不調」とはこの状態を維持できないこと、つまり毎日のストレスとうまく付き合い、能力を発揮して社会に貢献できなくなっている精神状態のことを言うわけです。
メンタルヘルス不調の代表的な疾患と言えば「うつ病」や「パニック障害」「適応障害」などが挙げられますが、メンタルヘルス不調とは必ずしもこれらの精神疾患のみを指しているわけではありません。WHOの定義によればストレスにうまく対処できない、十分に能力を発揮できない状態であれば「メンタルヘルス不調」なのですから、日常的にストレスを抱え不安や悩みのせいでなかなか気分が晴れない状態も全て含まれるのです。
メンタルヘルス不調の原因と症状
 メンタルヘルス不調は職場環境と個人的な要因とが重なり合って起こることが殆どです。例えばもともと人付き合いの下手な人が職場内の難しい人間関係に直面する、あるいは生活管理の悪い人が沢山の仕事を任されて残業続きになる、など等。同じ職場、同じ立場で仕事をしていてもメンタルヘルス不調を発症する人としない人がいるのも、このためです。
メンタルヘルス不調は職場環境と個人的な要因とが重なり合って起こることが殆どです。例えばもともと人付き合いの下手な人が職場内の難しい人間関係に直面する、あるいは生活管理の悪い人が沢山の仕事を任されて残業続きになる、など等。同じ職場、同じ立場で仕事をしていてもメンタルヘルス不調を発症する人としない人がいるのも、このためです。
いずれにしてもメンタルヘルス不調を発症すると、最初は寝つきが悪い、簡単な仕事でもミスが増える、何をするのも面倒くさい、食欲がない、お酒の量が増える、等の本人しか気づかない兆候始まり、やがて仕事上の義務を怠りがちになる、電車に乗ったりすると不安や緊張で倒れそうになる、付き合いが悪くなり遅刻・早退・欠勤が増える、表情が乏しく口数が減る、など周囲の人も気づくほどの症状が見られるようになります。
まとめと改善策
今回は主にストレスによって様々な不調を生み出すメンタルヘルス不調について記事を書いてまいりました。文中にもあるようにメンタルヘルス不調は起こりやすい人がいる反面、誰にでも起こる可能性があるものですから、心当たりがある場合は重症化しないように注意しましょう。
例えばその改善策として、メンタルヘルス不調の兆候に気づいたなら、まずは健康的な生活習慣を意識してみると良いでしょう。例えば良質な睡眠を摂る、規則正しい食習慣と運動を心がける、深酒をしないといったことで疲労の蓄積を防ぐことができ、これが気持ちを前向きにしてくれる可能性があります。
他にも自律神経の乱れを整えるため、整体などの専門機関に受診するのも良いでしょう。また職場環境が大きな問題となっているなら、上司や職場に設置されている相談窓口などに相談するのもお勧めです。
しかしながら、メンタルヘルスの不調などは他人からはよくわからないのはもちろん、自分でも気づかないうちに患っていて、会社に行けない、仕事ができない、などなにかしらの行動が起こせなくなるような事象が起こってから事態に気づくことが多くあり、その理由は初期症状では会社を休まないような真面目な方に発症しやすい傾向があるからです。
またそういった方々はメンタルヘルス以外にも精神疾患を起こしやすいので、ストレス発散の方法と一緒に、自分の限界値や自分には出来ない事などキチンと線引きして仕事や人間関係に取り組むようにしましょう。








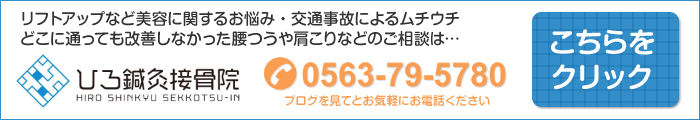
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません