モートン病の原因と予防法・ポイントは足の横アーチ!
 身体の健康を害す要因は日常生活における食事や姿勢、運動の有無など様々にありますが、今回はそんな中でも足指の裏側に痛みやしびれが起こるモートン病という疾患について記事を書いていこうと思います。
身体の健康を害す要因は日常生活における食事や姿勢、運動の有無など様々にありますが、今回はそんな中でも足指の裏側に痛みやしびれが起こるモートン病という疾患について記事を書いていこうと思います。
モートン病は簡単に言えば足の筋肉が加齢や運動不足によって落ちてしまうことによって起こるのですが、先のように日常生活において忙しくしていると身体の健康には気を付けられても足の健康にまでは気が回らないものです。
しかし、どのような疾患でも同じですが、原因を発見せず、軽症だからと放置を続けているとそれが原因で慢性的な痛みを生み出してしまうことも考えられます。当記事をお読みいただきご自身にも当てはまる場合は出来る限り改善できるように努力しましょう。それでは記事を始めてまいります。
モートン病の原因は?
 足の中指と薬指の間にしびれや痛みを感じる、モートン病。モートン病の原因は主に、足の横アーチの緩みや消失にあります。
足の中指と薬指の間にしびれや痛みを感じる、モートン病。モートン病の原因は主に、足の横アーチの緩みや消失にあります。
私たちの足は前から(指側から)見た場合、親指と小指を接地点として真ん中がやや浮いたような、半円アーチを描いています。基本的にアーチ状のものは衝撃や上からの重みに対して強く、足の場合この横アーチのおかげで体重を支える際の負荷が軽くなり、歩行時には衝撃を吸収してバランスを維持したり、足を踏み出すための推進力を生み出したりすることができるわけです。
ところがこの横アーチは長期にわたるハイヒールや幅の狭い靴の使用、また体重増加や足の靭帯・筋肉の低下によって緩んだり失われたりすることがあります。というのも足の横アーチは、5本の指から踵へとそれぞれ伸びる「中足骨」を横同士で繋いでいる「深横中足靭帯」によって形成されているのですが、踵の高い靴でいつもつま先立ち状態になっていたり、幅の狭い靴でつま先部分がギュッと圧迫されていたりすると、深横中足靭帯が引き伸ばされてアーチ型を保つことができなくなってしまうのです。
また体重が増えればそれだけ深横中足靭帯に負荷がかかることになりますし、加齢や運動不足で筋肉や靭帯の強度が低下すれば、やはり体重を支えきれなくなって横アーチが徐々に失われていくことになります。
こうして横アーチが失われると、深横中足靭帯の下を通っている神経が地面に押し付けられることになるため、圧迫されて痛みやしびれを感じるようになるのです。
モートン病を予防するには?
したがって、モートン病を予防するにはまず適切な靴を選び、深横中足靭帯に負荷をかけないようにすることが大切です。先の細い靴やハイヒールを避け、自分の足のサイズと幅にピッタリ合うものを選びましょう。ウォーキングシューズは足の健康を考えて作られていますから、できればウォーキングシューズを普段履きにするのがおすすめです。靴底が厚めで踵がしっかりと固定されていて、かつ素材が少し硬めのものを選ぶと良いでしょう。
またすでに触れてきたようなものだけでなく、モートン病の原因となる足の横アーチが崩れてしまうと、偏平足や外反母趾などにもかかりやすくなり、その結果、余計な箇所に負荷がかかることでタコや魚の目など異物が形成されてしまったり、足が疲れやすくなる、かかとに痛みが出る、あるいは足の裏を一直線に走る足底腱膜などに炎症が起こる足底腱膜炎などにもかかりやすくなるので足の指を上手に使い深横中足靭帯に負担をかけない歩き方をすることも大切です。
まとめ
 今回は加齢や運動不足あるいは硬い靴を履き続けるなどの理由で発生するモートン病について記事を書いてまいりました。運動不足というと身体全体の問題であるように考えられますが、筋肉が衰えることによってこのような問題が起こる、ということもお分かりいただけたと思います。
今回は加齢や運動不足あるいは硬い靴を履き続けるなどの理由で発生するモートン病について記事を書いてまいりました。運動不足というと身体全体の問題であるように考えられますが、筋肉が衰えることによってこのような問題が起こる、ということもお分かりいただけたと思います。
また本文では靴や運動不足の説明に注力しましたが、日ごろ行っている歩き方を見直すことでモートン病の予防をし、足の健康を守ることもできます。例えば以下のような歩き方を参考にしてみましょう。
モートン病が再発しないためにも、前述した、靴選びを見直す、ふくらはぎのストレッチをする、足裏のトレーニングをする、ということは重要です。
その中でも歩き方は大きく影響するので、少し歩き方を見直すようにしてみましょう。
まずまっすぐな姿勢のままで踵だけで立てるかチェックしてみてください。踵でたつとふくらはぎが伸ばされて、お尻をつきだしたり後ろにそっくり返るような気がしますが、頑張って踵でまっすぐ立てるようになってください。お腹の奥の筋肉が使われているのがわかりますか? 体幹の筋肉がしっかりと使われ、ふくらはぎこれができるようになると、普段歩くときもしっかりと踵に体重がかかる時間が長くなり、前足の負担が軽減できます。
(中略)
基本的には踵で着地し、片足に全体重が乗るときにはまだ踵から土踏まず付近に体重がかかっていて、次の足にうつることに初めてつま先が使われる、という感覚です。イメージ的には「踵で虫をつぶすように歩く」「蹴るというより踵で押し出す」感覚で歩くと、足や膝に負担をかけずに長く歩けるようになります。
引用:ドイツ足の健康館


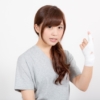





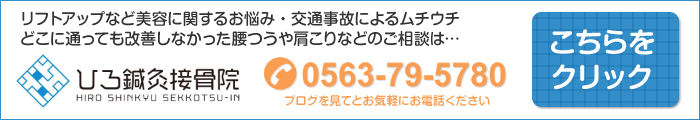
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません