腕のしびれが気になる?頸肩腕症候群!
 身体にとって悪影響を及ぼす行為と聞くと、思いつくのはデスクワークをしている方やトラック運転手のように座りっぱなしであったり、日々、重たいものを持ち上げている運搬業者の方などは腰や肩にコリや痛みを抱えそうなイメージがあると思います。
身体にとって悪影響を及ぼす行為と聞くと、思いつくのはデスクワークをしている方やトラック運転手のように座りっぱなしであったり、日々、重たいものを持ち上げている運搬業者の方などは腰や肩にコリや痛みを抱えそうなイメージがあると思います。
本日はどちらかといえば前者の方に起こりやすい頸肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)という不調について記事を書いていこうと思います。この疾患は疲労がたまりにたまって起こる過労性疾患の一つに数えられるもので漢字からもわかるように肩と腕に痛みやコリ、しびれ、手指の痛みなどを発症します。
過労性疾患は休息か原因の排除を行わなければいつまでも痛みやコリが続いてしまうことが特徴的ですから、本文の内容がご自身に当てはまるという方はなるべく早く問題解決を行えるように努力しましょう。それでは記事をはじめてまいります。
頸肩腕症候群とは?
 冒頭でも触れていますが、この疾患は漢字からもわかるように頸(けい:首)肩、腕にかけてコリ・痛み・しびれなどが起こるものです。具体的に原因を言えば、それらの箇所の筋肉が硬直することで神経を圧迫してしまい、不調となって現れます。
冒頭でも触れていますが、この疾患は漢字からもわかるように頸(けい:首)肩、腕にかけてコリ・痛み・しびれなどが起こるものです。具体的に原因を言えば、それらの箇所の筋肉が硬直することで神経を圧迫してしまい、不調となって現れます。
例えばデスクワークをしている方は日々、パソコンを打っているのでそれらの箇所に不具合が出るものと考える方が多いですが、そうではなく「同じ姿勢を続けている」ことが大きな原因なのです。
ですから家にいて、ソファに長時間横になっていたり、ずっと同じ姿勢でスマホをみている、ゲームをやっている、などでも頸肩腕症候群は発症します。またこの疾患が重症化していくと、肩や腰の血流も悪くなりますから、これによって疲労物質が流れにくくなり、さらに筋肉のコリが進行してしまう、という悪循環にもつながります。
頸肩腕症候群を予防するには?
これには「休息」と「原因の排除」が最も効果的なのですが、まずはご自身の状態について考えてみましょう。例えば最近、寝ても眠気が冷めなかったり、一日中だるさが続いたり、集中力が著しく下がったり、身体が上手く動かせなかったり、という症状は疲労が蓄積している合図と認識しましょう。
次に「休息」と「原因の排除」ですが、それらが身体にとって必要なものであると認識していても、実際には仕事はなくなりませんし、医師から診断された病名でなければなかなか休むことは難しいものです。
ですから前述のように「同じ体勢」でずっといない方法やちょっとしたストレッチでこの問題を解決しましょう。これは例えば一時間に一度程度、椅子から立ち上がったりして姿勢を変えるだけでも疲労の蓄積具合はかなり異なりますし、日常的に以下のようなストレッチをすることで、筋肉をほぐし、疲労物質を流すことができます。
胸をひらいてスマホ姿勢を改善
横向きに寝て、股関節とひざを曲げます。両腕を胸の前に伸ばし、両手のひらを合わせます。下半身を横に向けたまま、上半身をひねって上の腕で下の腕をなぞりながら胸の方へ引き寄せます。最後に胸をおおきく開きます。腕を伸ばすときは、無理にひじを伸ばす必要はありません。反対側も同様に行います。
体幹を鍛えてスマホ姿勢を改善
あおむけに寝て、ひざを肩幅に広げて立てます。両手は胸の上に置きます。息を吐きながら、お尻・腰・背中の順で徐々に上げていきます。無理のない範囲で上げられるところまで上げたら、その状態を3秒間保ち、背中・腰・お尻と逆の順で戻します。シールを少しずつはがしていくイメージで、尾てい骨から背中にかけてゆっくり上げていくのがコツです。
なで肩さんの肩こり解消筋トレ
両手と両ひざを床につきます。両手は肩幅に、両脚は腰幅に開きます。顔を前に向けながら、腰を落としていきます。その状態を3秒間保ったら、頭を下に向けながら背中を丸めるようにして腰を引き上げていき、その状態を3秒間保ちます。おへそを真、下真上に動かして、肩が前後しないよう意識しましょう。
引用:NHK健康チャンネル
まとめ
 今回は首、肩、腕などにしびれや痛みを発生させる頸肩腕症候群について記事を書いてきました。文中にもあるようにこの不調の改善には休息と原因の排除が欠かせないわけですが、仕事をすぐに変えることは難しく、自分の出来る範囲のことをまずはやってみることが肝要です。
今回は首、肩、腕などにしびれや痛みを発生させる頸肩腕症候群について記事を書いてきました。文中にもあるようにこの不調の改善には休息と原因の排除が欠かせないわけですが、仕事をすぐに変えることは難しく、自分の出来る範囲のことをまずはやってみることが肝要です。
今回はストレッチを引用してみましたが、ストレッチよりもジョギングやスポーツが好きという方はもちろん、それでも構いません。古くから言われているように運動を日常生活に取り入れることは身体の不調だけでなく、内臓の健康や病気の予防にもつながりますし、昨今では精神疾患もジョギングなどの運動によって予防できることがわかってきています。
なお最後になりますが、肩などに痛みがある時に、肩をぐるぐると回したりする方が多くいらっしゃいますが、肩こりの原因が実は、背中や首など一見すると関係ない所にあることもしばしばありますから、時間に余裕がある方は専門家に一度、相談してみるようにしましょう。








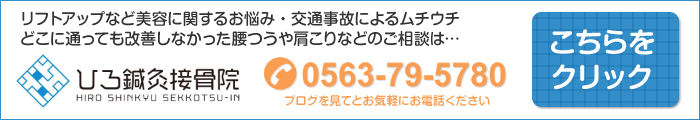
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません