これって依存症?依存症の定義と実例
 自分の意志ではやめる、あるいは自制することができないことを依存症と呼びます。たとえばそれはアルコールや薬物に始まり、万引きや痴漢などの犯罪行為または昨今では若者のゲーム依存というのも大きな社会問題となっています。
自分の意志ではやめる、あるいは自制することができないことを依存症と呼びます。たとえばそれはアルコールや薬物に始まり、万引きや痴漢などの犯罪行為または昨今では若者のゲーム依存というのも大きな社会問題となっています。
今回の記事では改めて依存症とはどのようなものであるのか、ということであったり、依存症が起こってしまう脳の仕組みなどについて記事を書いていきたいと思います。依存症は当事者はもちろん周りにいる方も苦しめる病気ですから、問題が小さなうちに早期発見・早期改善できるように努力しましょう。それでは記事を始めてまいります。
依存症とは?
 「アルコール依存症」や「薬物依存症」など「依存症」と言う言葉を聞くことは少なくありませんが、「依存症」の定義や種類、症状について正しく具体的な知識を持つ人はそれほど多くないため、自分や家族の状態が「依存症」なのかどうか分からない、という人もいるようです。
「アルコール依存症」や「薬物依存症」など「依存症」と言う言葉を聞くことは少なくありませんが、「依存症」の定義や種類、症状について正しく具体的な知識を持つ人はそれほど多くないため、自分や家族の状態が「依存症」なのかどうか分からない、という人もいるようです。
「依存症」とは「特定の物事に頼ることをやめることができない状態」であり、その対象物の多くは頼りすぎることで少なからず人の心身の健康や生活を脅かすことになるため、「やめなければいけないと分かっていてもやめられない」つまり自分の思考や行動をコントロールできない状態にあります。中には「『依存症』は心の問題、『中毒』は物理的な悪影響を受けている状態」と区別する人もいますが、基本的には「依存症」も「中毒」も同じこと。悪影響を受けているにもかかわらずやめられないのが、依存症なのです。
依存症には大きく分けて、アルコールや薬物、ニコチン、カフェインなど対象物が物理的な形を伴う「物質系」と、ギャンブルやダイエット、買い物など物理的な形のない特定の行為や関係を対象物とする「非物質系」の2種類があります。中には薬物や窃盗(万引き)などそれ自体が違法なものもありますが、対象物となるものの多くはそれ自体違法な物事ではなく適度であれば全く問題のないものであるため、「依存症」になっているのかどうかの判断が難しいところです。
そのため家族など周囲の人が気づいて専門家に相談し、医学的な診断基準を満たしていると判断されてはじめて「依存症」と診断されるケースが殆ど。ただし対象物によっては(特に非物質系の対象物に多い)、医学的な定義や診断基準が存在していないこともあります。
依存症の例
依存症の中でも最も一般的なのが、アルコールや薬物依存症でしょう。アルコールや薬物の依存症に関しては国際的な診断基準もあるため、比較的簡単に有無を判断することができます。判断基準としては、以下の6項目のうち3項目以上が当てはまるかどうか。
□アルコールや薬物を摂取したいという強い欲求がある
□量を控えよう、あるいはやめておこうと思ってもコントロールできない
□摂取しないと震えや不眠などの離脱症状が出る
□以前の摂取量では酔わなくなった・効かなくなった
□対象物の摂取に生活が占領されている
□悪影響が出ていると分かっているのにやめられない
これらの項目のうち3つ以上が同時に見られるなら、「依存症」と診断されます。
まとめ
 今回は様々な依存症について記事を書いてまいりました。文中にもありますが、依存症はその種類によって他人に迷惑をかけてしまうものもあれば、犯罪になってしまうもの、そして自分の命をなくしてしまう原因の一つにもなります。
今回は様々な依存症について記事を書いてまいりました。文中にもありますが、依存症はその種類によって他人に迷惑をかけてしまうものもあれば、犯罪になってしまうもの、そして自分の命をなくしてしまう原因の一つにもなります。
しかしいずれの依存症であっても、その行為に依存してしまう発端は人間関係や金銭問題、ストレスなどが大半を占めるといわれています。ですから依存症を早く治さないといけないという認識を持つよりは自身が依存してしまう原因について一考してみると少しは楽になれるかもしれません。
また下記では依存症に関わる脳の仕組みについて厚生労働省が出している文章を引用しておりますので、依存症の一歩手前あるいは改善を望まれる方はご一読ください。
脳の仕組みを知りましょう。
なぜ自分の意志ではやめられない状態になってしまうのか。
その鍵は脳にあります。
まずは脳の仕組みについて、依存対象物質の一つであるアルコールの摂取を例にして学びましょう。
私たちが物事を考えたり感じたりできるのは、脳の中で神経細胞がさまざまな情報伝達を行っているからです。
しかし、アルコールが体内に入ると、脳に侵入し、情報伝達の働きに影響を与えます。
アルコールだけでなく、薬物でも同様ですが、これらの物質を摂取すると、私たちの脳内ではドパミンという快楽物質が分泌されます。
この快楽物質が脳内に放出されると、中枢神経が興奮し、それが快感・よろこびにつながります。この感覚を、脳が報酬(ごほうび)というふうに認識すると、その報酬(ごほうび)を求める回路が脳内にできあがります。
アルコールを例にしましたが、ギャンブル等で味わうスリルや興奮といった行動でも、同じように脳の中で報酬を求める回路が働いているのではないかと言われています。
引用:厚生労働省 HP








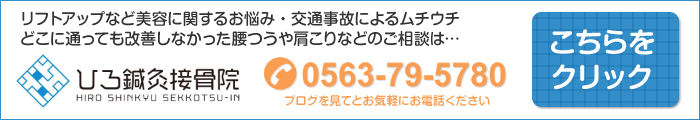
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません