突然の鋭い痛み!神経痛とは?
 私たちの身体というのは本当に不思議なものです。何もない時であれば特に意識もせずに生きていられるものですが、時にいままで経験したことがないような痛みを発するときもあります。
私たちの身体というのは本当に不思議なものです。何もない時であれば特に意識もせずに生きていられるものですが、時にいままで経験したことがないような痛みを発するときもあります。
今回は身体に走り回る神経が異常を感じて痛みを出す神経痛について記事を書いていきたいと思います。この病気のつらさは経験しないとなかなか理解できないものだと思いますが、先のように時に痛みを感じることもあればしびれや麻痺という形で顕現するときもあります。また神経痛の中には原因がよくわからないものもありますが、予防することで痛みを回避することができるのも事実ですから、気になる方は予防に向けた取り組みを行いましょう。それでは記事を始めてまいります。
神経痛とは?
 突然鋭い痛みが走り、治まったかと思いきやまた再発・・・を繰り返す、「神経痛」。神経痛とは「頭痛」や「腰痛」のように症状を表す言葉で、その名の通り神経の支配領域で急に起こる激しい痛みの総称です。
突然鋭い痛みが走り、治まったかと思いきやまた再発・・・を繰り返す、「神経痛」。神経痛とは「頭痛」や「腰痛」のように症状を表す言葉で、その名の通り神経の支配領域で急に起こる激しい痛みの総称です。
そもそも「神経」には脳と脊髄で構成され各種神経の中枢となる「中枢神経」と、そこから枝分かれし体中に張り巡らされている「末梢神経」とがあります。末梢神経には更に体温調節など自分の意思とは関係なく働く「自律神経」と運動神経など自分の意思でコントロールできる「体性神経」とに分かれており、この体性神経には痛みや熱さなどの触れた時の感覚を伝える「感覚神経(知覚神経)」も含まれます。これら末梢神経が体内外から受けた刺激を中枢神経に伝えたり、中枢神経から出される指令を受け取ったりして、生命活動に必要な生体反応を可能にしているのです。
従って「神経痛」とは、より正確に言えば感覚神経が受けた刺激を中枢神経に伝えることで感じる、痛みや痺れのこと。この「何らかの刺激」には圧迫や炎症、疾患などがあり、刺激の元となっているものがハッキリしているものを「症候性神経痛」、刺激の元となっている原因がハッキリしないものを「特発性神経痛」と呼びます。とはいえ神経痛は原因が特定できる場合が殆どなので、一般に「神経痛」というと「症候性神経痛」を指すことが多いようです。
主な神経痛の種類
神経痛を起こしやすい部分は主に「坐骨神経」と「肋間神経」「三叉神経」で、それぞれに「坐骨神経痛」「肋間神経痛」「三叉神経痛」と呼ばれます。
このうち坐骨神経は、腰椎下部から始まり膝で別れて足の裏まで1m以上も伸びている人体最長の末梢神経で、このため坐骨神経が刺激されるとお尻からふくらはぎ、踵まで広範囲に痛みを感じることがあります。その刺激の元となっている原因は、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など。中でも多いのが椎間板ヘルニアで、飛び出した椎間板が坐骨神経に当たり圧迫することで神経痛を引き起こします。
肋間神経は肋骨の間を走っている末梢神経で、左右に12本、合計24本ありますが、症状は左右どちらかの背中から胸にかけて出ることが殆どです。肋間神経の原因はやはり椎間板ヘルニアか事故などによる骨折、またウィルス感染や内臓疾患が原因になることもあります。
三叉神経とはこめかみから目、顎、頬と三本に枝分かれした顔にある神経で、動脈硬化などで膨張した血管に三叉神経が刺激されることで起こります。また原因不明であることも多く、特発性の場合、ストレスなどによる自律神経の乱れが関係しているのではないかとも考えられています。
まとめ
 今回は様々な神経痛について記事を書いてまいりました。文中にもありますが、神経痛は普段は何も意識せずに勝手に動いてくれているものですから、一度、不調が現れると生活にも大きな影響を及ぼします。
今回は様々な神経痛について記事を書いてまいりました。文中にもありますが、神経痛は普段は何も意識せずに勝手に動いてくれているものですから、一度、不調が現れると生活にも大きな影響を及ぼします。
ですから起こってから改善を急ぐよりも普段から予防の意識を持っておくことが大切です。例えば下記のようにそれぞれにあったアプローチ方法を実践する習慣をつけ、痛みのない毎日を送れるように努力しましょう。
坐骨神経痛の予防:何より腰痛の予防を!
坐骨神経痛を予防するには、原因のほとんどを占める腰椎間板ヘルニアの予防、つまりは腰痛にならないことが一番です。ストレッチや運動などで腰への負担を減らし、筋力をつけ、腰痛にならないような生活習慣をつけましょう。
(中略)
三叉神経痛の予防:ストレスをなくそう
三叉神経痛は突然発症することが多く、特に予防が難しい神経痛の一つです。とはいえ、原因不明の特発性神経痛と同様、疲れやストレスによる自律神経の乱れが関与しているともいわれています。次の項目を参考に、日ごろから適度な運動とストレスをためない生活を心がけたいものですね。
適度な運動とストレスのない生活習慣を身につけよう
病気の予防には、バランスのよい食事、適度な運動、十分な睡眠やストレスをためないなどの正しい生活習慣が何より大事です。また、冷えは血行不良になり、すべての神経痛の痛みを増長させます。冬の寒さ対策、夏の冷房対策、そしてからだを冷やさないような食生活を心がけましょう。
引用:くすりと健康の情報局








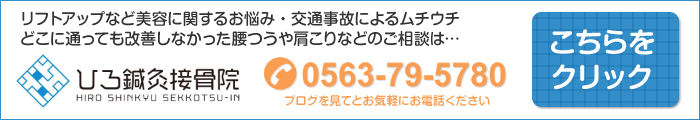
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません