脊柱管狭窄症の原因と予防
 腰痛の原因は様々なものが考えられますが、例えばその腰痛が下半身のしびれを伴って現れるようになったときは脊柱管狭窄症の疑いがありますから、すぐに専門家にかかるようにしましょう。
腰痛の原因は様々なものが考えられますが、例えばその腰痛が下半身のしびれを伴って現れるようになったときは脊柱管狭窄症の疑いがありますから、すぐに専門家にかかるようにしましょう。
この脊柱管狭窄症とは後述していきますが、簡単に言えば背骨を走っている神経に圧力がかかることで痛みやしびれあるいは簡単な歩行障害などを引き起こします。いつまでも痛みがなく健康に過ごしていたいというのはどなたも思うことですが、ある程度の年齢に差しか返れば誰にでも起こる可能性があり、またすでにそれらの症状が出ているという方は改善に向けた努力をしましょう。
それでは一緒に確認してまいりましょう。
脊柱管狭窄症とは?
 しばらく歩くと太ももからふくらはぎ、脛にかけて痛みや痺れが出、しばらく休むとまた歩けるようになる・・・という歩いたり休んだりを繰り返さなければならない症状を「間欠跛行」と言いますが、この間欠跛行と共に腰を後ろに反らすと痛みがひどくなり、逆に前かがみになると楽になるという症状が見られる場合、「脊柱管狭窄症」が疑えます。
しばらく歩くと太ももからふくらはぎ、脛にかけて痛みや痺れが出、しばらく休むとまた歩けるようになる・・・という歩いたり休んだりを繰り返さなければならない症状を「間欠跛行」と言いますが、この間欠跛行と共に腰を後ろに反らすと痛みがひどくなり、逆に前かがみになると楽になるという症状が見られる場合、「脊柱管狭窄症」が疑えます。
「脊柱管」とは背骨を構成するリング状の「椎骨」が縦に連なってできた管で、この管の中を太い神経「脊髄」が通っています。この脊髄の通り道である脊柱管が何らかの原因で狭くなってしまうのが、「脊柱管狭窄症」。神経の通り道が狭くなって神経を圧迫することで痛みや痺れなどの症状が起こるわけですが、脊柱管は首の骨「頸椎」から腰の骨「腰椎」まで続く長い管であるため、そのうちどの部分が狭くなっているかで症状の現れる箇所も異なります。とは言え最も狭窄症を引き起こしやすいのは腰の骨であるため、「脊柱管狭窄症」と言えば大抵「腰部脊柱管狭窄症」を指すことが多いよう。冒頭で述べたような症状も、腰椎に起こる脊柱管狭窄症の代表的なものです。
脊柱管狭窄症の原因と予防
脊柱管狭窄症の直接の原因は骨や椎間板の変形、黄色靭帯の肥厚などで、これらが脊柱管を狭くして中の神経を圧迫します。では何が骨や椎間板の変形、黄色靭帯の肥厚を引き起こすのかというと、この原因は1つではありません。
例えば加齢によって体内の水分が乏しくなり柔軟性に欠けるようになると様々な組織に変性が起こりますが、だからと言って全ての年配者が脊柱狭窄症になるわけではないでしょう。加齢だけでなく、腰を使う作業や腰に負担をかけるスポーツを繰り返し行っていたり、腹筋力が足りず反り腰の姿勢になっていたり、肥満で腰椎に慢性的な負担をかけていたりすることで、加齢による劣化と共に徐々に脊柱管狭窄症へと発展していくのです。
従って加齢は避け得ないものの、他の引き金となる要因は日々の心がけで避けたり軽減したりすることが可能です。ポイントとなるのは、腰に負担をかけない、特に腰を反らす姿勢を極力避ける、ということ。例えば下に置いてある荷物を持ち上げようとする場合、膝を伸ばしたまま腰だけ曲げて抱えるのではなく、膝と股関節を曲げてしゃがむ姿勢になり、腰の位置を低くして持ち上げましょう。こうすることで負担が腰だけに集中するのを避け、股関節や膝関節にも分散させることができます。
また前述の通り肥満も脊柱狭窄症の原因となるため、高カロリーの食品は避け栄養バランスの良い食事をとることも大切です。
まとめ
 今回は神経に圧力が加わることで痛みやしびれを引き起こす脊柱管狭窄症について記事を書いてまいりました。文中にもあるようにこの疾患の大きな原因の一つは加齢による衰えをあげることができます。なかには腰痛やしびれが加齢からくるものであれば仕方がないとあきらめてしまう方もいらっしゃいますが、適切な運動や食生活の改善がきちんとされればまだまだ改善は可能です。
今回は神経に圧力が加わることで痛みやしびれを引き起こす脊柱管狭窄症について記事を書いてまいりました。文中にもあるようにこの疾患の大きな原因の一つは加齢による衰えをあげることができます。なかには腰痛やしびれが加齢からくるものであれば仕方がないとあきらめてしまう方もいらっしゃいますが、適切な運動や食生活の改善がきちんとされればまだまだ改善は可能です。
特に脊柱管狭窄症は日ごろからのケアが何よりも大切ですから、例えば気づいた時に下記のようなストレッチをするなどして、しっかりとケアしてあげるようにしましょう。
脊柱管狭窄症におすすめのストレッチ
脊柱管狭窄症のストレッチの重要な目的は、次の 2 点です。
・狭くなっている神経の通り道を広げて、神経の圧迫を取り除く
・腰や足の付け根の、関節の動きを妨げる筋肉の凝りをほぐす
これらを踏まえた具体的なストレッチの方法を 、ポイントを交えながら3 つ紹介します。
1 ,膝かかえストレッチ
初めに紹介するのは、神経の通り道を広げたり、背中の筋肉をほぐしたりするストレッチです。
・仰向けになり両膝をかかえます
・太ももをお腹に近づけるようにします
・ 15 秒キープします
・ 5 回ほど繰り返します
POINT:太ももを近づけるタイミングで息をフーッと吐き出しましょう。
2 ,正座ストレッチ
次も、膝かかえストレッチと同じ効果が期待できるストレッチです。
少し難易度が高くなります。
・四つ這いの状態で背中を丸めます
・手の位置は変えずに徐々に膝を曲げていきます
・背中を丸めるように意識して、正座のような姿勢になります
・また四つ這いの姿勢にゆっくり戻ります
・ 5 回ほど繰り返します
POINT:先ほどのストレッチと同じように、正座をするときは息を止めないようにして、リラックスをしましょう。
引用:リペアセルフクリニック






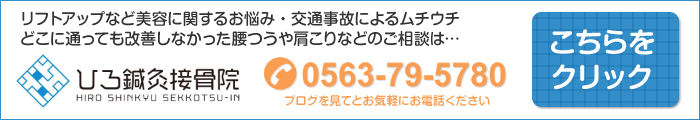
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません