疲労骨折が起こりやすい場所と改善法
 日常生活ではルーティンを繰り返しているという方、多いと思います。反対に毎日毎日、異なったことをしているという方のほうがすくないのではないでしょうか。
日常生活ではルーティンを繰り返しているという方、多いと思います。反対に毎日毎日、異なったことをしているという方のほうがすくないのではないでしょうか。
もちろんその生活スタイルは何も悪くありませんが、身体や筋肉においては毎日同じことを繰り返すというのはあまりいい事ではありません。筋肉は一度疲労するとある程度の期間をおいて休息させてからでないと徐々に硬くなっていき、その結果、疲労が限界に達するとケガという形で身体に限界を知らせます。
今回のテーマである疲労骨折などはその最たるものですから、本文を読まれて少しでも疲労骨折について知っていただければ幸いです。それでは記事を始めてまいります。
疲労骨折が起こりやすい部位
 一度の大きな衝撃で骨にひびが入ったり完全に折れてしまったりする通常の「骨折」とは異なり、日々行うスポーツや労働などによって慢性的に骨に負荷がかかり、やがて亀裂が入ってしまうのが「疲労骨折」。初期の段階では特定の動作をしない限り痛みはなく、また運動中もそれほど強い痛みではないためそのままスポーツを継続してしまうことが多いのですが、こうして骨に負荷を与え続けることによってどんどんと症状が悪化してしまうと、日常生活でも痛みを感じるようになってしまいます。
一度の大きな衝撃で骨にひびが入ったり完全に折れてしまったりする通常の「骨折」とは異なり、日々行うスポーツや労働などによって慢性的に骨に負荷がかかり、やがて亀裂が入ってしまうのが「疲労骨折」。初期の段階では特定の動作をしない限り痛みはなく、また運動中もそれほど強い痛みではないためそのままスポーツを継続してしまうことが多いのですが、こうして骨に負荷を与え続けることによってどんどんと症状が悪化してしまうと、日常生活でも痛みを感じるようになってしまいます。
疲労骨折はこのような原因から特に下半身の骨に発症することが多く、その中でも発症頻度が高いのは足の甲にある中足骨と脛にある脛骨、腓骨と言われています。
中足骨の疲労骨折は、ジャンプや突然の切り返しなど素早い動きが求められるスポーツ、例えばバスケットやサッカーなどで起こりやすい骨折です。中足骨は親指側から「第1中足指」と数えて小指側の「第5中足指」まで合計5本ありますが、その中でも第2、第3中足指で起こる疲労骨折は「行軍骨折」とも呼ばれバスケットボールやバレーボール、剣道、陸上競技をする人に多く見られます。一方第5中足骨に起こる疲労骨折は「Jones(ジョーンズ)骨折」と呼ばれ、こちらはサッカー選手に多いとされています。
脛骨は膝から足首までの2本の骨のうちの太い方の骨のことで、特に脛骨の上から1/3の部分、あるいは下から1/3の部分の疲労骨折は走る競技で起こりやすいため、「疾走型」と呼ばれます。一方脛骨の中央1/3の部分の疲労骨折はバスケットボールやバレーボールなどのジャンプするスポーツに多く、このため「跳躍型」とも呼ばれています。
腓骨は脛にある2本の骨のうち細い方で、こちらも脛骨の疲労骨折と同様「疾走型」と「跳躍型」に分けられます。とは言え脛骨と比べると腓骨の疲労骨折はそれほど多くはありません。
疲労骨折の改善法
前述の通り疲労骨折は早い段階ではそれほど痛みがないため無視して運動を続けがちですが、そのままだと悪化して完全に折れてしまう危険性もあるため、気づいた時点で運動を一時的に中止する必要があります。
早い段階で運動をやめて安静にしていれば自然治癒力により骨も修復されるため、保存療法が取られる場合がほとんどでしょう。骨折箇所によっては無意識に負担をかけてしまうことを防ぐため、ギブスやコルセットで固定することもありますので、なるべく早めに専門家に相談するようにしましょう。
まとめ
 今回は継続した負荷によって起こる疲労骨折について記事を書いてまいりました。文中にも出てきますが本来は下半身に多い当疾患ですが、加齢や骨粗しょう症などをはじめとする骨が弱くなるような疾患にかかると今度は上半身、特に背骨などにも表れるようになるので注意が必要です。
今回は継続した負荷によって起こる疲労骨折について記事を書いてまいりました。文中にも出てきますが本来は下半身に多い当疾患ですが、加齢や骨粗しょう症などをはじめとする骨が弱くなるような疾患にかかると今度は上半身、特に背骨などにも表れるようになるので注意が必要です。
また意外に思われるかもしれませんが、骨折の予防というと牛乳などカルシウムを摂取することが一番の近道と思われる方が多いと思いますが、実は骨は運動することによっても強化されていきます。詳しくは下記引用をご覧ください。
- 骨力を上げる運動
私たちの骨は、新しい骨を作る「骨芽細胞」と古い骨を壊す「破骨細胞」がバランスよく働くことで、丈夫に保たれています。しかし、年齢とともに骨芽細胞による骨形成能力は低下。破骨細胞の働きのほうが活発になるため、骨力が徐々に低下します。これを防ぐには運動が必要です。運動で骨に刺激を与えると、骨芽細胞が活性化して、新しい骨を作る指令が下されます。日々の生活に簡単な運動を取り入れて、骨力の向上を目指しましょう。
- 柔軟性
久しぶりに運動すると、転倒してケガや骨折をすることがあります。その背景にあるのが、柔軟性の低下です。ストレッチで柔軟性を保ち、からだを動かせる範囲を広げておくことが大切です。
- 筋力
つまずく、ぶつかる、倒れるといったアクシデントがあっても、自分を支える筋力があれば踏みとどまることができます。継続的に筋力トレーニングを行いましょう。
- バランス能力
バランス能力が低下すると、正しい姿勢を保ったり、安定して立ったり座ったりするのが難しくなって、転倒しやすくなります。片足立ちをしたり、足指を鍛えたりして、バランス能力を鍛えておく必要があります。
引用:痛みWITH








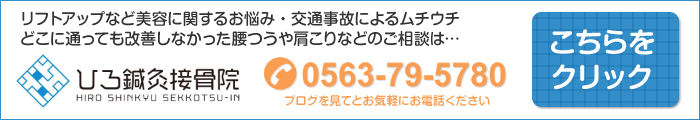
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません